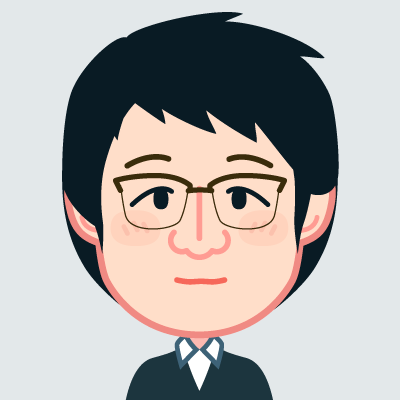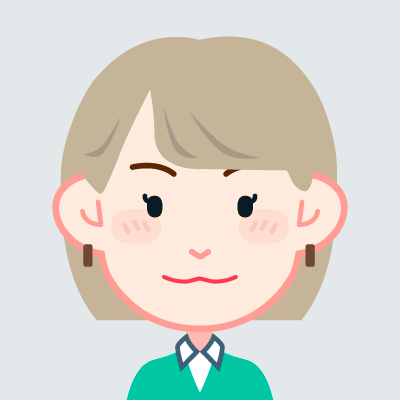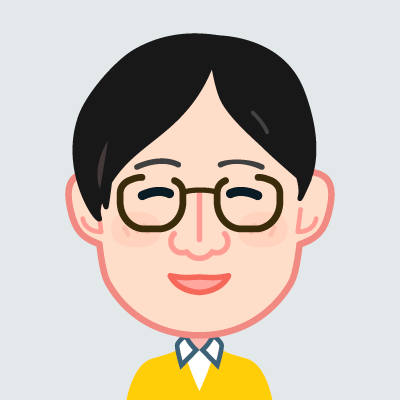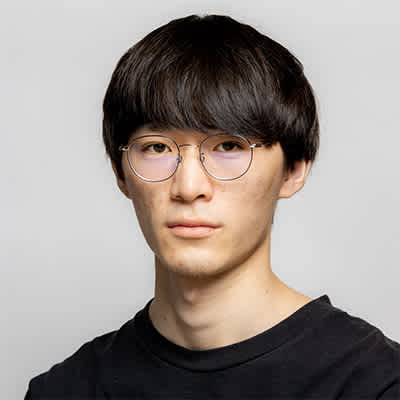Business Architects(ビジネス・アーキテクツ、以下BA)は、スペシャルオリンピックス日本(SON)のポッドキャスト配信に共感し、その取り組みを後押ししています。第1回の座談会では、「SONの声に触れて感じたこと」「配信内容の魅力」について語り合いました。
そして迎えた第2回では、ポッドキャストという音声配信の手法そのものに焦点を当て、動画配信との違いや、ビジネスにおける効果・可能性について掘り下げます。
対談に参加したのは、BAの若手メンバー4名。エンジニアの大日、社内情報システムの田村、ささげプレス(カスタマーサクセス)の佳菜、Webマーケティングの飯塚が、それぞれの立場から率直な意見を交わします。今回、ディレクターの谷口がファシリテーターを務め、自然な進行でメンバーの意見を引き出していきます。
職種も視点も異なるメンバーたちが、それぞれの業務感覚をもとに「伝えるメディアの違い」について語り合う本音の座談会。ビジネス活用に興味のある方にも、「伝え方を選ぶヒント」をお届けします。

インタビューを受けた人
![プロフィールアイコン(イラスト):システムエンジニア 田村]()
- 田村サービスサポートグループ/システムエンジニア(ビジネス・アーキテクツ)
2023年に派遣社員としてビジネス・アーキテクツに入社。 情報システム業務に従事し、社員の機器やライセンス管理を受け持つ。 2025年より正社員として勤務。
![プロフィールアイコン(イラスト):ささげプレス 佳菜]()
- 佳菜サービス企画グループ/ささげプレス(ビジネス・アーキテクツ)
アパレル業界で販売員・EC担当を経て、2022年にビジネス・アーキテクツに入社。現在はアパレル業界で培ったコミュケーション能力とECの知識を活かして、ささげ支援システム「PANAMA」の業務に従事。
![プロフィールアイコン(イラスト):マーケター 飯塚]()
- 飯塚セールス&マーケティンググループ/マーケター(ビジネス・アーキテクツ)
システム開発会社で金融プロジェクトに配属し、6年勤務したのち、社内システムエンジニアとしてデータ見える化、社内DX、業務効率化を担当。2024年にビジ��ネス・アーキテクツへ入社し、セールス&マーケティンググループでマーケターとして業務稼働の見える化や、GA4のデータ分析に携わっている。
![プロフィールアイコン(写真):フロントエンジニア 大日 慧]()
- 大日 慧Webエンジニアリンググループ/フロントエンドエンジニア(ビジネス・アーキテクツ)
2021年に株式会社BAXSに入社。SaaS型ソフトウェア「PANAMA」のデザインや、フロントエンドの業務を経験し、経験値を積む。 2025年に会社が統合されてからは、お客様のサイトのオーサリングやサイトの保守・運用業務を行なっている。自分の持ち味をいかし、デザインもできるエンジニアを目指して日々勉強中。
動画と音声、受け取り側の印象はどう違うのか?
「突然ですが、ふだん動画と音声、どちらをよく利用していますか?」みなさんの日常での利用シーンなども合わせて教えてください。
大日:基本、動画が多いですね。ゲームやスポーツなどをYouTubeとかで利用します。音声もたまにですが、最近は好きなアーティストのラジオも聴いたりしています。動画も音声も、別のことをしながら聴くことが多いです。
田村:音声だけで情報を入れるということは少なくて、逆に動画が多いですね。ゲームの配信やツール、映画、本の紹介・考察の動画をよく見ます。比較的長めの動画を倍速にもせずに見ています。
佳菜:私もほぼ動画ですね。私はせっかちなので、田村さんとは違ってメイクや料理の動画などの情報を得たい場合は倍速を使いがちです。ただ、出演者が目的だったりする場合は、倍速にせずにじっくり見ます。ラジオやポッドキャストも聴くことはありますが、どちらかというと好きなアーティストが出演しているときなど、限定的な目的で聴くことが多いです。
飯塚:動画を多く利用します。動画編集など、趣味で作業をしている際にも動画を流し、BGMとして利用しながら作業をすることが多いです。動画自体に目を向けず、ミュージックビデオなど流れている音声だけをポッドキャストみたいに楽しむ使い方をしています。

皆さん、動画を主に利用されているのですね。では、動画と音声で、伝わり方や体験ってどう違うと感じますか?
飯塚:動画は、視覚と聴覚の両方に訴えるため、インパクトが強く、記憶に残りやすい印象があります。一方でポッドキャストのような音声は、動画に比べると記憶に残りにくいかもしれませんが、“ながら聞き”や作業BGMとして利用することができ、興味がある話題が流れてきたら耳を傾けたりしています。
佳菜:動画が与えてくれる体験という観点では、飯塚さんの言う通りですよね。発信側が伝えたいことを視覚的にも補完してくれるので、こちらが意図を誤解しにくく、記憶にも残りやすいと感じます。特に“伝える力”という点で、映像の説得力は大きいと思いますね。ただ、その分、“情報が強すぎる”と感じることもあります。
逆に音声は、明確に物を伝えるというより、受け取り側の想像力に委ねられる部分があるところが面白いです。人に意見を聞いたりするのにも向いているかもしれません。また、じっくり音声だけを聴くという点でも、音に集中することができるのも音声の魅力だと思っています。
田村:音声のみの場合は、音に集中して聞いてもらい、情報を伝えられることがメリットかなと思います。ただ、受け取り側が渡された情報を100%吸収しきるためには、動画などの映像がある方が情報量が多くなり浸透率が良くなると思いました。
映像があった方が与える側が渡したい・与えたい情報量を高めることができると思います。
大日:CMなどの短い動画などは、音声含めて記憶として定着しやすいと思いますね。長い動画だとすべてを記憶するというのは、さすがに無理があると思いますけど。音声は、佳菜さん同様に、受け手側に委ねられるところが大きく、想像力をもって聴くことでより話題を楽しめると思います。SONのポッドキャストも想像しながら聴くことでより興味をそそられました。
利用シーンも違いますよね。視聴者やリスナーなど受け取り側に与える印象はどう変わると思いますか?
田村:動画であれ音声であれ作り込みができているのであれば、そこまで違いはないと思います。
動画には視覚情報があり、情報量に差があるので情報の吸収率という点で差が生まれると思います。また、音声なら“ながら聞き”が多いなど、利用するメディアに集中できる状況かどうかでも、情報を100%受け取れるかどうかが変わってくるのかなと思います。
佳菜:集中力などの点では、動画の方が情報量が多いので受け取り側が大変だと思っています。ただ、知りたいことが明確になってる場合は、動画の方がコンパクトに情報を得ることができると思いますし、結果的にはタイパもいい気がします。
逆にリラックスしたシチュエーションなどでは、音声の方が受け取り側の負担も軽く、情報が得られると思います。
大日:たしかに動画は、音声に比べ集中力を使うこともあって、最近は短めの動画で情報を集約して情報を伝える手法が流行っているんだと思います。たとえば、TikTokとかショート動画のような短くてパッとわかる情報が、多くの人に受け入れられているんじゃないかなと思います。
音声は、聴いている時間は長いけど、その点は“ながら”に最適ですよね。じっくり聴くときにも、耳だけで情報を取り入れるからこそ、集中しているときはすごく深く入り込める感じがあります。
飯塚:みなさんがすでにおっしゃっている通り、動画は直感的に情報を取り入れるのに向いていて、コスパ・タイパよく情報を取得できると僕も感じています。
ただ、動画と音声の利用シーンというより、受け取り側の目的にあったコンテンツによって利用方法が変わるんだと思います。たとえば、英会話を学びたい人は、音声に耳を傾けるとか。
たしかに、そうですね。目的に応じた選択肢があるという点では、アクセシビリティの観点も関係してきますよね。たとえば耳が聞こえない方は、動画の動きや字幕で内容を楽しんでいたりしますし、電車の中でイヤホンを忘れたけど、どうしても推しの動画配信が見たい!なんて時も、同じように字幕を頼りにするなど、その方の状況によって楽しみ方が変わってきますね。

動画配信と音声配信、それぞれのメリット・デメリット、ビジネスでの活かし方は?
ビジネス視点で考えると、音声と動画にはどんな強み・弱みがあると思いますか?
飯塚:動画の強みは、やはり“伝えやすさ”だと思います。動画は、視覚情報も音声情報も得られるので、何かを学ぶことにも適しています。発信側も直感的に伝えられるのが大きなメリットですね。操作や製品の使い方など、言葉では伝わりづらいことも映像であれば直感的に伝えられるし、記憶にも残りやすいと思います。
少し前に参加したAI博覧会というカンファレンスでも、ほとんどのサービス説明や発信に動画が使われていました。
一方で、動画制作や編集は時間がかかるうえに、コストが高くつきます。また、技術者の確保も課題となることが多いです。その面では、音声配信に強みがあると思います。少ない時間と低いコストで発信できるのは、魅力的ですね。SONのポッドキャストでも「なぜポッドキャストなのか?」という話の中で、低い予算で施策が達成できた話が触れられていますよね。
田村:自分がビジネスでやると仮定すると、資料を作ってビジネスやサービスの実績や紹介をすると思うんです。
そういう点だと、音声のみで伝えるというシーンはあまり思い浮かばなかったです。文字から視覚情報を得ることはできないので、伝えたい情報をまんべんなく伝えるなら動画が主になるだろうと思いました。
ただ、ターゲットの年齢や性別などによって使いわけることはありだと思います。映像は「きちんと伝えきりたい内容」や「商品紹介」などに向いているし、音声はもう少し雑談的で、ブランドの“空気感”を醸成したり、継続的にファンとつながる手段に合う気がします。
音声で伝えることも、SONポッドキャストのパーソナリティのやまだひさしさんのように伝えるのが上手な人じゃないと、品質的にハードルが高いとも感じます。
大日:個人や小規模チームでも配信できる手軽さや親近感の面で、音声にメリットがあると思いますね。音声の方が始めるハードルが低く、距離感も近く温かみを感じることができると思います。その点、動画は事前準備が必要で、企画・撮影・編集すべてに工数がかかる分、アウトプットの完成度には期待できますよね。高いクオリティで伝えたいなら動画というふうに達成したい目的によって使い分けることが必要だと感じます。
飯塚:最近は、動画がつくれるだけじゃなく、サムネイルのデザインや動画の見やすさという点でも評価されますし、動画の品質はかなり再生数に影響すると思いますね。そういう点では、コストや制作にかける時間が増す方向にはありますね。
大日:たしかに、サムネイルが良ければ見てみるし、動画の内容が良くて、しゃべりが面白ければ、次の動画の再生にもつながるし、自分でも発信してみようかなとなりますね。そういう点では、音声より動画の方が影響力が大きいですね。
田村:ゲームだけではなく本や映画などの解説動画で、自分と違う解釈を自分の中に取り入れることで新しい視点があり面白いなと感じています。
それらの動画でもサムネイルなどで、目的の情報がそこに含まれているかどうかがわかる方が再生につながりますよね。
佳菜:みんなが動画を作り込む話をしていて、たしかにそうだなと思って聞いてました。
前職でよく物販系のライブ配信をしていたので、動画というとライブ配信のイメージが強くて、ライブ配信は作り込んだ動画や音声配信の間くらいなのかなと思います。
ライブ配信だと、今まで上がったコストや時間の負荷軽減は可能だと思いますし、ライブ配信だと、出演者の表情や会社の雰囲気がなんとなく見えるのはいいところだなと思ってます。
動画といっても、ライブ配信や生中継なのか、編集した動画なのか、他にもお店のサイネージなどいろいろありますね。音声についてはどうですか?
佳菜:音声は、制作コストが圧倒的に低いというメリットがあるのは、皆さんと同じ意見です。それに加えると、動画だと顔出しがあるので出演者の出演許可が取りづらいのですが、音声のみであれば出演許可も比較的取りやすいと感じます。
ビジネス面のメリット・デメリットという点だと、企業の動画を見ようと思う人ってすでに、企業に対して何らかの興味をもっている人だと思うんです。興味がない人などの潜在顧客以下の人にもリーチしたいという目的であれば、気軽に聞ける音声で情報を届けることにメリットがあるんじゃないかなと思います。
受け取り側とどういう距離感を取っていきたいという視点でも音声、動画を使い分ける視点が必要ですね。では、ビジネス効果を考えた音声と動画の「効果的な棲み分け」ってどう考えたらいいと思いますか?どうやったらバズる(効果を得られる)でしょうか。
大日:短くまとめた動画とか、基本的には短く要点をまとめた動画がバズるシーンをよく見かけます。音声は想像力を掻き立てることが得意なので、たとえばラジオの合間に、アーティストの音楽情報などターゲティングした広告を挟みます。そうやって「広告の商品はどういうものなんだろう?」と受け取り側が気になる情報を与えることで、その商品のことをよく知らない人にも、情報を探して公式サイトを閲覧させるなどの次のステップに誘引することが可能だと思います。その点では、動画よりも手軽でありながら認知度の向上も期待できると思います。
田村:自分の見識が浅いのもあるとは思いますが、音声でバズってるというのは見たことがないので市場的に厳しいのかなと感じます。
ビジネス効果的に狙うんだったら、ショート動画に注目すると思います。
佳菜:バズってるのは99%動画ですよね。動画配信はキャッチーだとバズるんですよね。ただTikTokやインスタグラムのリールとかで、動画じゃなく曲だけバズるという形もありますよね。単調な曲とかバズりやすい曲の傾向はあるように感じます。そういう意味でも“きっかけ作り”には音声がすごくいいと思ってます。
飯塚:効果的な棲み分けという点では、動画の場合、ウェビナーや宣伝、広告などは視覚的に情報を得られるため、記憶に残りやすく、伝えたいこともわかりやすく伝えることができるため効果的だと考えています。
音声については、視覚的情報が不要な教材などの発信を行うことに向いていると思います。たとえば、出勤時やすきま時間に音声教材を利用し、手軽に情報を入手できます。そういった棲み分けを行うことで、それぞれのメディアで成果が生まれると考えています。

業種やターゲット、シチュエーション別のメディア選択
どんな業界やターゲットに効果的だと思いますか?
飯塚:先程の内容と重複しますが、音声の場合、英会話など語学学習やニュース等の情報発信などに向いていると考えています。
動画は多岐にわたると思います。飲食の場合は最近ではメニューを電子掲示板に映して宣伝を行ったりCMで動画として宣伝を行っています。また、Web制作ではウェビナーとして動画を活用したりと、多くの利用業種が存在すると思います。
佳菜:目に見える製品がある業界は、動画が効果的だと考えます。自分が以前関わっていたファッション系の商材では、着用感やサイズ感は映像じゃないと伝わらないですし、共通認識がない製品の情報を伝えたい場合に、音声だけだとどうしても発信側と受け取り側に認識の齟齬が生まれてしまいます。
逆に朗読やBGMのような形にならないクリエイティブなものを扱う業種は、音声だけの方が向いていると思います。受け取り側の一人ひとりがイメージや意見をもつこともできるし、制作側もその意見に耳を傾けることができます。また、多くの人に共通認識がある情報を伝えるような業種は、音声のみでも効果的に伝えられると思います。
田村:ターゲットについては、音声だと“ながら”作業が多く、かつ自由な時間がある層にフィットしてるのかなと思います。
パッと思い当たるのは、長距離ドライバーなどかなと。最近は本の朗読をしてくれるサービスも豊富にありますし、音だけを聴くという需要はもちろんあると思います。
大日:特に動画が効果的な業種は、ゲーム業界や自動車業界など商品を実際に見せたときに魅力が伝わりやすい業種だと思います。ゲームは実際のゲーム画面やプレイしている様子を映すことで興味をもってもらいやすくなりますし、自動車は、ディテールや内装を知るところが購入してもらうための最初のステップだと思います。
音声が有効な業種は、音楽や音を伝えることを仕事にしている業界が一番向いていると思います。たとえば、アニメなどでは、出演している声優がラジオなどの音声コンテンツで発信することがメインとなっています。音楽業界もラジオなどで曲を試聴してもらい認知度を高められていると思います。音声を楽しむことがメインのコンテンツ・業界なので、もちろん音声の発信はとても有効的だと思います。
ポッドキャストが特に効果的だと思うシーンって、どんなときですか?
佳菜:前提として「ひとり時間」は間違いないと思っています。さらに“ながら”を考慮すると、通勤・通学や運動、運転など、手が塞がっていても耳が空いているタイミングですね。日常生活に自然に入り込めるのが音声の最大の強みだと思います。
飯塚:ポッドキャストなどの音声コンテンツを聴くために時間を確保し、集中して聴くことは少ないとは思います。そのため、ひとりで何かをしているときが一番効果的だと考えています。私も、作業中や移動時間、入浴中、寝る前に利用しています。
田村:私もどっしりと腰を据えてというよりは、何かをしながらというシーンが多いと思います。そして、作業をしながらでも情報が受け取れることが強みだと考えるので、皆さんと同じように、電車などの移動中や寝る前などが主に狙うべきシーンだと考えます。
大日:みんなが言うように、利用シーンが日常生活に紐づいたシーンが多い点は、ポッドキャストや音声配信の強みであると思います。
まずは、気軽に聞いてもらえるという接点から間口を広げていき、いろいろな人に幅広く聞いてもらうことができます。さらにSONのように、オリンピック選手のゲストなどを招いて話題性を高め、コンテンツへの興味換気を行うことも効果的ですよね。
バズるというのは外的要因が大きいですが、たとえバズらなくても、「発信する」という取り組みを地道に続けていくことで、多くの人にコンテンツを認知してもらえるようになるんだと思います。

まとめ:ポッドキャストと動画、それぞれの良さを活かした発信へ
動画がもつ「視覚的な説得力」や「記憶への残りやすさ」に対し、音声には「生活に溶け込む柔らかさ」や「想像力を刺激する力」があります。
SONのポッドキャストは、単に情報を発信する手段ではなく、「声」という人間的でパーソナルな媒体を通して、想いや考えを届けるユニークな試みです。
今後、BAとしても、こうしたメディアの特性を理解しながら、「伝えたいことをどう伝えるか」という視点で、クライアントにとってベストな選択肢を提案していきたい──
そんな前向きな思いが語られる、実りある座談会となりました。
これまでの座談会を通して、BAメンバーが感じた「音声配信の魅力」や「動画との違い」、さらには「どんな人に届けたいか」という思いを、少しでも感じていただけたでしょうか。今回の“ポッドキャスト聴いてみた座談会シリーズ”の第1回・第3回の記事では、それぞれ「SONの姿勢や考え方」、「アクセシビリティ」について異なるテーマで座談会を行っています。こちらもぜひご覧ください。
- “for”じゃなく“with”の世界へ——SONのポッドキャストで感じた社会のカタチ(第1回)
- 音声か?動画か?──ポッドキャストから考える“伝え方”の選択肢(第2回・本記事)
- みんなが使いやすいWebについて──SONの取り組みを通じて考えてみる(第3回)
SONのポッドキャスト全8回は、Podcast・Amazon Music・Spotifyにて配信中!
アスリート、スタッフ、ドリームサポーター、アスリートアンバサダーなど、それぞれの立場から語られるリアルな声には、きっと新しい発見があるはずです。
音声だからこそ伝わる“声”の力。
ポッドキャストを通じて、SONの活動や想いを感じてみませんか?
ぜひ、日常の中で耳を傾けてみてください。
TOKYO FMにてラジオ番組『5分では伝えきれないスペシャルオリンピックスの世界』がスタート
2025年7月からTOKYO FMにてラジオ番組『5分では伝えきれないスペシャルオリンピックスの世界』がスタートしました!
パーソナリティは、SON広報プロジェクトアンバサダーである「やまだひさし」さん。
SOに関わる様々な方をゲストに迎え、SONの魅力をもっと身近に感じられるように、楽しさや現状、応援の方法まで多角的にお届けするトーク番組です。共生社会のヒントがここに。
TOKYO FM 『5分では伝えきれないスペシャルオリンピックスの世界』
月曜〜木曜 20:55~21:00 ※7月1日(火)スタート
放送概要、放送ラインナップ、視聴方法などの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。
今後も、SONとの連携を通じて、“つながりを生むコミュニケーション”を社会に広げていくことができればと考えています。