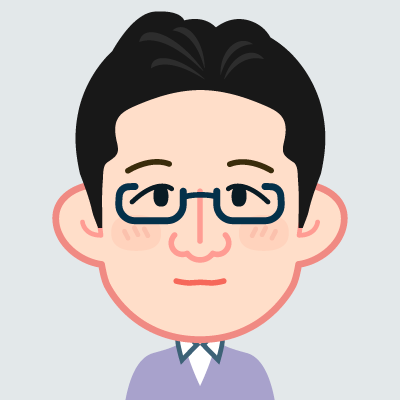ビジネスの世界では、優��秀な営業担当者のことを「エース」と呼んだりしますよね。商品やサービスの説明、デモなどをおこない、お客さまをクロージングする能力に長けた方を指すことが多い言葉です。
Webサイトがビジネスの中心となって久しい今、貴社のWebサイトは営業の主力として機能しているでしょうか?、「エース」級のパフォーマンスを出してくれているでしょうか?24時間365日休まず働く「最強の営業マン」になっているでしょうか?
優秀な営業担当者がお客さまを惹きつけ成約に繋げるように、Webサイトもまた、戦略次第で無限の可能性を秘めています。
本記事では、『Webサイトの営業力』について実践的な視点から解説します。
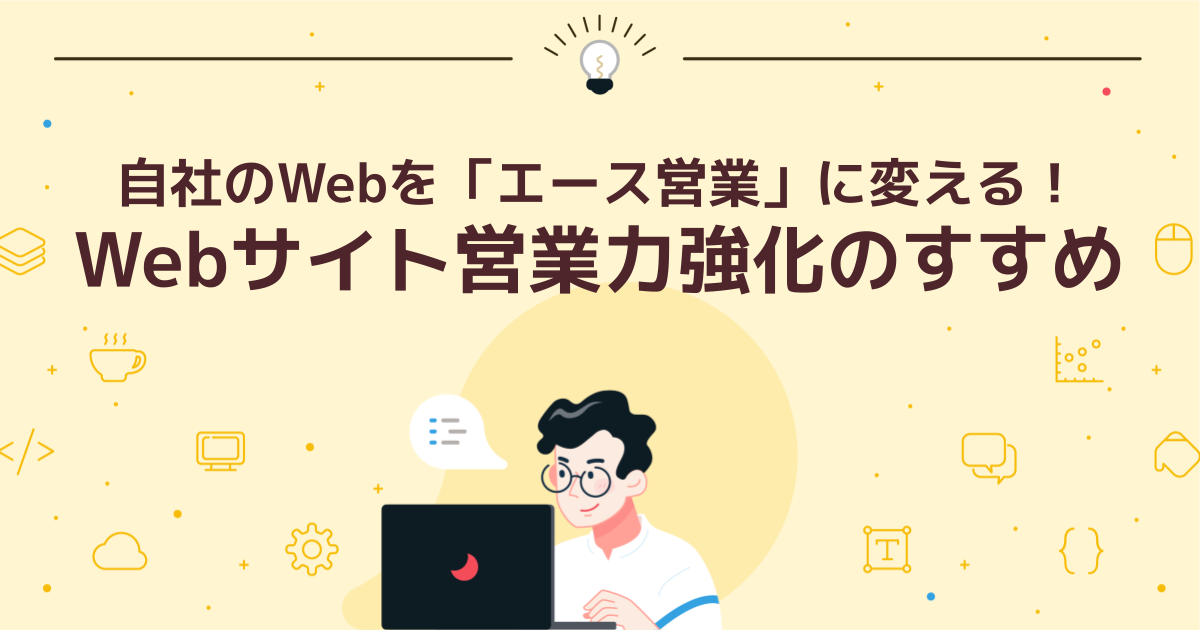
「Webサイトの営業力」とは何だろう?
そもそも「Webサイトの営業力」はどのように定義づけられるでしょうか?
営業力=「Webサイトを通じてお客さまになってもらう力」と定義できるでしょう。ただし、「お客さまになってもらう」といっても、最終段階までをWebサイトで完結する企業と、そうでない企業とではビジネス上のプロセスが大きく異なります。商談のアポイントやデモの依頼を受け付けることがゴールの企業と、最終契約・課金までしてもらうことがゴールの企業とでは、必要になってくるコンテンツも異なるでしょう。
契約がゴールとならないビジネスプロセスでは、Webサイトでは主にリード獲得のツールとして活用されます。それでも、Webサイトの営業力を高めることは、企業全体の売上向上に直結する存在だといえます。
Webサイトの営業力を構成する要素としては、「誰が、自社商品やサービスにおいてWebサイトでの情報提供を通じて興味を持ち、Webサイト上でどのような行動をして、結果として購入や契約、リアルの担当者へ引き渡されたのか・されなかったのか」となります。
この「Webサイトの営業力」の要素を上手に分解しその要素をチェックすることで、期待に対してのギャップや改善点のヒントを明確にできます。
「Webサイトの営業力 =(Webサイトに)訪れた方 × (情報提供された)コンテンツの閲覧 で (期待していた)行動を生むことができたか」と分解するとチェックポイントに近づけるかもしれません。
- 訪れた方=「誰が」「どこから」「いつ」
- 閲覧コンテンツ=「何を見て」
- 期待すべき行動=「何をしたのか(しなかったのか)」
このあたりにベースを設定してチェックポイントを探っていくことにしましょう。

誰が
サイト来訪者は「誰」でしょうか?「誰」といっても、具体的な個人名まではわからないので、取得できる指標で周りから推測を加えていくことになります。これでも意外と見えてくるものです。Cookieベースで動くMAツールやWeb接客ツールを導入していれば、さらにサイト来訪者像を可視化することができます。
新規訪問・リピーター
初めての訪問なのか、何度も来てくれている方なのか。その割合はどちらが多いのか。再来訪の場合、頻度はどの程度なのか。1か月あたりのアクティブユーザーという見方もできます。
気を付けたいのは、あくまでCookieにとってのということです。Cookieが削除されれば新規に戻ってしまいますし、Cookieを拒絶されていれば計測できないことは知っておくべきポイントです。
デバイス
端末は何か。BtoBの場合は PCが中心なことが多いですね。モバイル、タブレットでのアクセスの割合やモニターの解像度も一度は見ておきたい箇所です。
アクセス元
どこからアクセスしているのかにあたる部分です。物理的なエリアと、IPアドレスからわかる企業名とに分けられます。企業名を特定できれば、どの企業からのアクセスなのかより具体的に知ることができます。エリアからは、自社の商圏との重なりや、都心部への偏りも確認すべきポイントです。エリアに限定しない仕事をしているのに、東京都からのアクセスが70%を超えているなんてケースがあれば、本当にそれで良いのか一度立ち止まって考えてみるべきでしょう。
自社との関係性
アクセス元で、企業名が特定できれば、未来の顧客になりえる方なのか、パートナー候補なのかライバル企業なのかといった関係性が探れます。BtoBの場合、同業他社と思われる来訪者が、個人名義のメールアドレスで大量にホワイトペーパーをダウンロードしていくケースがたまにあるのですが、裏側でIPアドレスから会社名がバレて筒抜けなんてこともありえるわけです…。実際に起こりうるケースで注意が必要です。
デモグラフィック属性
Googleにログインしている人などの細かい条件は付きますが、 年代や性別、興味のある領域といった属性に関する情報もある程度把握が可能です。GA4でGoogleシグナルを有効にする必要はありますし、いろいろと条件付きの機能ではありますが、顧客の理解にはつながる項目になります。
どこから・いつ
Webサイトの来訪者が「どこから」やってきたかの部分です。Webの特性として「どこから」が追えますのでしっかり把握しておきたいところです。主に、流入元とランディングページの関係を中心に見ておきましょう。
流入経路
流入経路です。 広告経由なのか自然検索なのか、SNSなのか。BtoBでは少ないですが、BtoCの場合はアプリの起動も入ります。メールマガジンやQRコード、販促のチラシなどは正しく計測できていますか?しっかり設定しておかないと直接流入の割合が多くなってしまいます。構成比率にも留意したいところです。さらに、流入経路ごとに新規・リピーター比率やコンバージョン率、閲覧ページ数・滞在時間などを掛け合わせることができる大事な要素です。
自然検索
GA4だけではすべてを把握できずサーチコンソールと連携することが必要になります。Googleだけになってしまいますが、自然検索の詳細がわかるので設定しておきましょう。ここでは、指名キーワードと一般キーワードを見ていきます。社名やサービス名といった指名キーワードの検索ボリュームはどの程度でしたか?一般的なキーワードからの検索ボリュームは狙い通りでしたか?また、一般キーワードの中に、自社サービス検討時に検索で使うであろうキーワードは含まれていたでしょうか。SEOの有料ツールを導入していれば、ライバル企業と比べてどうなのかといったさらに詳細な部分まで探れますが、まずは自社サイトに絞って想定との乖離を探っていくべきポイントです。
加えて、検索経由のアクセスの総量は以前に比べてどうでしょうか?少し長期的な期間で見てみてください。検索経由のアクセスが減少傾向にある場合は、原因を分析しましょう。
また、自然検索の流入割合がほかの流入経路と比べ高すぎる場合は、流入経路の拡大を検討しても良いかもしれません。広告を打つでもしない限り流入経路の変更にはなかなか時間がかかることが一般的です。
キーワードと季節要因、ビジネスプロセス
自然検索が多い場合は、キーワードと自社のカレンダーや業界的なイベントカレンダーとの関係も見てみましょう。商戦期や大型イベント前後でキーワードに動きはあるでしょうか。
また、そのキーワードはビジネスプロセス上どのあたりを指し示す言葉でしょうか。検討の後半で必要になってくるキーワードなのか、前半、入口に近いあたりの言葉でしょうか。このあたりは次の項目「コンテンツ」の検討に大きく影響する箇所になります。
「誰」情報との掛け合わせ
複数回来訪者であれば、初回と2回目とでアクセス経路は異なるでしょうか。モバイル経由とPC経由でアクセスの仕方、サイト内行動に差はあるのか。埋められる差かどうか、乖離の程度も確認しましょう。
「いつ」の項目としては
文字通り、何月何日の「いつ」を知ることと、リピーターに限ってはどのくらいの頻度で訪れているかを確認しましょう。特にオウンドメディアを運営している場合は、記事の更新タイミングとリピートアクセスの間隔が揃っているかはチェックしたいところです。
何を見て
Webサイト訪問者は「どのページ(コンテンツ)を見ているのか」。その行動を分析します。
ランディングページ
アクセスにおいて最初に訪れたページをランディングページと呼びます。最初にどのページにアクセスしているのか。ここは重要な項目です。最も多いランディングページは、自社やサービスにとって最も読んでほしいページでしたか?「流入経路」や「キ-ワード」との掛け合わせでもランディングページは変わりますので、深堀していきましょう。
ランディングページと読んでほしいページにズレが生じている場合は、なぜズレが生じているのか、原因を把握し対策が打てるか検討が必要です。ページ上での対策が難しければ応急処置として、アクセスの多いランディングページから読ませたいページへの誘導を用意しましょう。
閲覧ページ
Webサイト全体でどのページが見られているのかの項目です。BtoBのサイトでは、1訪問あたりの閲覧ページ数は意外と多くありません。閲覧されたページに書かれている内容が自社ビジネスにおいて大事なポイント足りえるのか、望むべきゴールへ正しく誘導できているかを確認しましょう。
掛け合わせ
ランディングページだけでなく、流入経路(検索キーワードや他サイト)と閲覧ページの掛け合わせも確認しましょう。検索した意図が書かれているページにユーザーはたどり着けていたでしょうか。
滞在時間、スクロール
ランディングページを含めたページが役に立っているのかは「滞在時間」と「スクロール」で判断をしましょう。しっかりとページの最後の方までスクロールしてくれたのか、それによって滞在時間はどの程度だったのかはページにより異なります。長ければ長い方が良いという単純な世界ではありませんが、その値は想定内だったのか、想定を超えるほど面白くて滞在が長くなるのは○ですが、他の理由で長くなるのはNGです。
例えば、ページの最下部にCTAを置いているケースはいろいろなサイトでよく見られますが、ページ最下部までスクロールしてくれなければ意味がありません。こういった分析にも使えるのが「滞在時間、スクロール」の項目にもなります。
どんな行動をしたのか(しなかったのか)
最後は、サイト来訪者がWebサイト上でとったアクションについての部分です。ここでは、コンバージョンや資料請求など、成果に直結するアクションを指します。
CV率、フォーム通過率
例えば、資料請求がゴールなのであれば、その行動をしてくれたのかどうか。
フォームの入口までは来ているが完了していない、いわゆるフォーム通過率が悪い状態であれば、フォームの手直しをする必要があるわけです。
フォームの通過率を高める要素はいくつかありますが、取得している項目数との関連が高いため、取得した後使わない項目であれば削ってしまい、最小限の取得にとどめるなどの対策を講じることができます。
CTAクリック率
そもそもフォームへの誘導ができているかは、CTAの箇所にイベントを設定して細かく見ていく必要があるでしょう。正しい場所に正しいロジックで設置されているか。数は足りているのか、チューニングできそうかといった視点で見ていきましょう。
CVから見た行動
サイト解析をされている方なら100も承知ですが、サイト全体の訪問者におけるコンバージョン率/数は実はあまり高くありません。そのため、入口(流入)から出口(コンバージョン)を見るだけではなく、出口から入口をさかのぼって見ることをお勧めします。コンバージョンをした方に共通の閲覧ページがあれば、そのページで伝えている要素はユーザーに届いていることになるわけですから。
他の要素との掛け合わせ
これまでにご説明した、誰の要素(新規・リピーター)、どこからの要素(流入経路/自然検索のキーワード)、閲覧コンテンツとコンバージョンを掛け合わせることは最も重要な指標です。
Webサイトの営業力を高めるために
さて、長々とここまで、Webサイトの営業力をチェックする視点について解説してまいりました。少し長くなったので再整理しましょう。
Webサイトの営業力を磨くための3つの要素
①「誰が、どこから、いつ」=インバウンド力
「誰が」「どこから」「いつ」の要素は、すなわち引き込み力です。最近のはやり言葉で言えばインバウンド力と言い換えることができるでしょう。
インバウンド力としては、
- 流入元はどこか。期待通りの集客ができているか。
- 期待すべきアクション(レスポンス、コンバージョン)が取れている流入元は何か。
- アクセスが多いキーワードとアクションが取れるキーワードとで乖離が生じていないか。
- 期待される流入となるキーワードは設定されているか。そのキーワードで検索した方が期待するコンテンツは用意されているか。
- ビジネスプロセスに適したコンテンツは用意されているか。
- Webサイトのリピート来訪バランスは適切か。
といった自社サイトへどのようにユーザーを吸引できているかを中心に見ていくことになります。
②「何を見て」=アウトバウンド力
2番目は、「何を見て」に当たる部分です。アウトバウンド力と言い換えられるでしょう。自社が伝えたいことを、サイトにアクセスいただいたユーザーが理解できるように、発信できているのかが評価される要素になります。
- コンテンツは自社のビジネスプロセスに応じて適切に用意されているか。
- 見込客のビジネスプロセスに応じたコンテンツが多層的に用意されているか。
- 営業担当の資料には記載があるが、Webでは掲載していない情報はないだろうか。
- コンテンツは魅力的か。
- 自社・自社サービスの魅力は何か、伝えられているか、競合と比べて優位に立てているか。
- メールなどプッシュ施策は用意されているか。
ビジネスの役に立つために、優れた営業マンの役割を担ってもらうためにWebサイトがあるわけですから、お客さまに情報を届けることができているのかといった視点が重要になります。
③「どんな行動をしたのか」=レスポンス獲得力
最後が、レスポンスです。お客さまがどんな行動をしてくれたのか。それは期待していた行動なのかそうでないのか。ここを見極める要素です。
- 用意されているコンテンツでアクションは取れているか。
- 大小とりまぜたアクションは用意できているか。
- アクションは増やせるか。アクションする場所、数を増やすことで質を向上させられるか。
- アクションを作るために効くコンテンツ(情報発信)は用意されているか。
- ユーザーに行動喚起させるCTAやオファーは用意されているか。
- リードナーチャリングが可能か。
この大きく3つの視点で整理してみると、かなりスッキリ整理できるのではないでしょうか。
Webサイトの営業力を磨くための3つの要素。インバウンド力、アウトバウンド力、レスポンス獲得力。これら3つの力を強化し、Webサイトが営業のエースとして活躍できる状態を目指しましょう。
Webサイトの営業力を診断し、改善に活かしませんか
一方、自社だけでWebサイトの営業力をチェックし続け、改善していくのはなかなか骨が折れる作業です。そこで、ビジネス・アーキテクツでは、Webサイトの営業力を診断して改善に役立てるサービスをご用意しました。

先ほどの3つの視点など様々な視点から、貴社サイトの営業力を診断し、改善にお役立ていただけます。売上アップに直結する実践力のある方法を知りたい方は、今すぐ資料をダウンロードしてください!