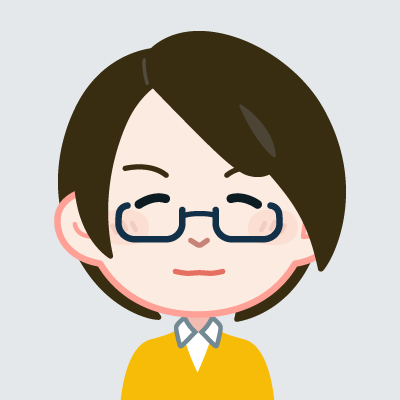今、「企業が声で語る」時代が来ています。
その中で、スペシャルオリンピックス日本(以下、SON)は、音声コンテンツを通じて新しい形のコミュニケーションに挑戦しています。
ポッドキャストという誰もが親しみやすいメディアを通じて、“伝える”だけでなく“つながる”ことを目指すSONの試み。
今回、Business Architects(以下、BA)のメンバーでSONのポッドキャストを実際に聴き、SONという組織の魅力や活動、BAとの関わり、そして音声メディアの可能性について座談会形式で語り合いまし�た。
登場するのは、SONプロジェクトに深く関わるメンバー4名。ポッドキャストに込められた想いや、そこから感じた未来への展望をお届けします。

インタビューを受けた人
![プロフィールアイコン(イラスト):デザイン&コミュニケーションサービス事業部 事業部長 小山]()
- 小山デザイン&コミュニケーションサービス事業部/事業部長(ビジネス・アーキテクツ)
toCサービス、toBサービス拠点マネジメントを通してサービスの複数拠点の運営管理を担当。またtoBサービスの企画立案などで企業向けサービスの企画・開発を行う。Business Architectsには2019年にジョイン。大規模サイトのアカウントマネジメントや金融系サイトのプロジェクトマネジメントなど多くのプロジェクトを手掛ける。
![プロフィールアイコン(写真):ディレクター 谷口]()
- 谷口アカウント&ディレクショングループ/ディレクター(ビジネス・アーキテクツ)
埼玉県出身。Bangkok University (BUIC)にて、グラフィック、アート、デザインの基礎を学び、ウェブデザインの技術に強い関心を持つ。2016年大学卒業後に日本に帰国し、ビジネス・アーキテクツに入社。海外経験で培った英語力(TOEIC:860点)や社交力、柔軟性を活かして、社内とクライアントの架け橋として、グローバル案件や、コーポレートサイトの運用/リニューアルのディレクションに従事。特にCMSを使ったウェブサイト構築や運営管理の分野で活躍を始める。
担当領域は、主にCMSで構築した企業サイトの制作進行管理を中心に、情報設計、PDCA改善提案まで。趣味は、音楽鑑賞とカフェ巡り。
![プロフィールアイコン(写真):ディレクター 森住]()
- 森住アカウント&ディレクショングループ/グループリーダー/ディレクター(ビジネス・アーキテクツ)
2003年よりビジネス・アーキテクツに参加。大規模サイトのフロントエンド実装で多くの実績を積む。2008年からは実装者として稼働する傍ら、フロントエンドディレクターとして大企業向けのコーポレートサイト、サービスサイトの実装要件定義、実装ガイドライン策定、アクセシビシティガイドライン策定など、プロジェクト初期段階から運用設計まで、フロントエンド領域の設計業務に携わる。2016年には、業種業態や規模の異なる複数のサイトを運用するための専任組織リテンション・デザイン部を立ち上げ、部長としてワークフロー策定からプロジェクト管理、組織マネジメント全般を担当。2017年より大手ICT企業のオンサイトチームに参加。サイト運用業務からオウンドメディア構築やイントラサイト構築・運用をディレクション。技術とトレンドの観点から提案し続けている。
![プロフィールアイコン(写真):ディレクター 佐藤]()
- 佐藤アカウント&ディレクショングループ/ディレクター(ビジネス・アーキテクツ)
接客業からWeb業界へ転職。マークアップコーダーを経験し、その後2024年にビジネス・アーキテクツに入社。入社後は運用フェーズのプロジェクトをメインにディレクターを担当している。
SONってどんな組織?その魅力に迫る
「突然ですが、SONってなんの略かわかりますか?」SONがどのような組織か、ご紹介ください。
小山:SONは「Special Olympics Nippon」の略ですね。ポッドキャストの中でも、渡邊 浩美(SON常務理事)さんと岩沼 聡一朗(SON理事)さんがお話しされていましたが、1960年代にアメリカで始まった、知的障害のある方々にさまざまなスポーツのトレーニングや競技の機会を提供する活動、いわゆる「スペシャルオリンピックス(SO)」がルーツになっています。その活動を通じて、社会参加を促すというのが大きな目的です。
日本では1980年代にその活動が始まり、1994年に現在の「スペシャルオリンピックス日本」として正式に組織化されました。今では、知的障害のある方だけでなく、その家族や支援者を含め、さまざまな立場の人が関わる“共にある”活動として広がり続けています。
SONの魅力はどこにあるとお考えですか?
佐藤:ポッドキャストを聞いていて印象的だったのが、「Withにする」というスタンスです。助けてあげるとか与えるという発想ではなく、一緒に取り組んでいくという考え方。知的障害をもつ方と社会交流をしていくという姿勢が、とても素敵だなと感じました。
森住:アスリートだけじゃなくて、ボランティア、アンバサダーなど、さまざまな人が関わって成り立っている活動。それぞれが欠かせない存在として、自然と支え合う関係があるということが、SONの魅力のひとつだと思います。
谷口:人と人が支え合って成り立つ活動そのものが、SONの魅力だと感じました。ポッドキャストの第1話で紹介されていた“ケネディ家の庭で始まった”というエピソードも、活動の根源にある温かさを象徴しているようで、強く心に残りました。
小山:ポッドキャストでは、「オリンピックス」の「s」が複数形になっている理由にも触れていましたよね。これはトレーニングや競技会が単発のイベントではなく、継続的なプロセスとして日常の中に組み込まれていることを示しています。そして、支援する側にとっても成長の機会がある。私や富本さんが行ったボランティア活動に関わる人たちにも成長の機会があると感じました。そういう意味合いでも複数の「s」なんだろうと思います。SONが目指す“インクルージョン”は、単なる理念ではなく、こうした実践の中で自然と実現されているんだと感じました。
「2024年 第8回スペシャルオリンピックス日本 冬季ナショナルゲーム」に大会ボランティアとして参加いたしました
SONとBAの関係、その歴史とプロジェクトの舞台裏
SONとBAはどのような経緯で関係を築いてきたのですか?
小山:最初の取り組みは2019年6月、BAがナショナルパートナーとしてSONの公式Webサイト制作を担当したことがきっかけでした。Webサイトの企画から制作、コンテンツ設計、運用支援まで、全面的に携わるようになって、そこから関係が深まりました。私もちょうどそのタイミングで入社していて、自分のSNSにも「こういう活動に関われるのは嬉しい」と投稿したのを覚えています。
谷口:私は、2018年にSONのWebサイトの運用を担当し始めたのがきっかけです。東京で行われた「2019年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ」の日本選手団の最終合宿に取材として同行する機会もありました。アスリートの方々やご家族と直接触れ合うことで、現場の熱量を肌で感じることができたのは、今でも忘れられない体験です。
他にも、SONが大切にしている「ユニファイドスポーツⓇ(Unified SportsⓇ)」という取り組みを広めるためのスペシャルコンテンツの制作と2023年のWebサイトリニューアルにも携わりました。
森住:その後、Webサイトのリニューアルフェーズで私がプロジェクトを引き継ぎました。このリニューアルは、BAとしてもひとつの節目で、単なる受託ではなく「どうすればSONの活動がもっと多くの人に届くか」を真剣に考えるプロジェクトだったと思っています。
佐藤:私は、比較的最近このプロジェクトに加わりました。運用担当として毎月Webサイト更新を行う中で、SONのスタッフの方々が本当に熱心に「伝えたいこと」を共有してくれるんです。例えば、「今、Be with allⓇというスローガンを打ち出しているんです」、「こういうことを伝えたいんです」、「こういうWebサイトをもっといろんな人に見てもらいたいんです」など、熱量のこもった共有をいただきます。その熱量に応えたいという気持ちで、日々の更新にも責任をもって取り組んでいます。ボランティア参加も機会があれば、参加してみたいです。
谷口:ボランティア参加といえば、立川のBリーグ公式戦にて行われた「SOデー」イベントにもスタッフとして参加させていただきました。
このイベントは、意識活性の側面があり、Bリーグ公式戦の試合途中にSONのアスリートたちが会場に入場し、ショートゲームが行われたり、PR映像が流れました。SONを知らなかった会場の観客にも、SONの取り組みが深く伝わった素敵なイベントでした。私は、早朝から会場入りし、試合前のアスリートやSONの方と交流させていただいたり、インタビューも間近で見学させていただきました。身近に接する機会を通じて、たくさんの力をいただきました。今でも心に深く残る、忘れられない思い出です。

これまでの取り組みの中で、どんな学びや印象に残る出来事がありましたか?
佐藤:ある月にSONのWebサイトへの流入が急増したことがありました。その原因を調べていったら、韓国のアイドルが身につけていたブレスレットが、SONとパートナーシップ連携していたブランドのものだったということがわかりました。X(旧Twitter)でその話題が拡散されて、多くの人がSONの活動を知るきっかけになっていたんです。Webサイトのアクセス解析を行うことで、何がSONのWebサイト認知につながるのか、どういう広報活動をしていったらより多くの人に知ってもらえる道筋になるのか、という点が今後の活動のヒントになると感じました。
谷口:私が印象に残っているのは、取材記事を読んだアスリートのご家族から「子どもがこんなふうに活動している姿を見られて感動した」とフィードバックをいただいたことです。Webという手段が、単に情報を伝えるだけでなく、感動を生む媒体になり得るんだと実感しました。Webサイトを通して何かを伝えたり発信することが、私たちの役目なので、私の中では、これがひとつの成功事例なんじゃないかなって思いました。Webサイトを通して喜んでもらえる人が画面の先にいるということを考えるところにも無限の可能性を感じますし、今回のポッドキャストのように、Webサイト以外の方法でも何か私たちに挑戦できることがあるのではと、今後の可能性を感じた出来事でした。
森住:SONは、私たちのクライアントワークの中でも一般企業のプロジェクトとは少し仕事の質が違います。それは、SONの価値観とか成果の考え方とかが一般企業と質が異なっている点にもあると思います。NPOや支援団体との関わりは、「支援するとは何か」「成果とは何か」をあらためて考える機会になります。SONのプロジェクトに関わることで、自分の仕事への向き合い方も変わったと思います。その点では社内メンバーの意識に大きく影響がありましたよね。
小山:社内でも「SONと一緒にやっていることがもっと広まってほしい」という声は多いです。リニューアルプロジェクトの影響もあり、社内でも関わる人が圧倒的に増えましたね。エンジニアやデザイナーの人も含めて、わりと多くの人が関わるようになったことが大きなきっかけだと感じます。
入社した頃は、スポンサーになりたてで社内関係者も少なく、ボランティアの応募が谷口さんともう一人位しかいなくて。当時は、あまり自分ごと化、会社ごと化していなかったのが、リニューアルプロジェクトなどの多くの施策を経て、全社的な取り組みに徐々になりつつあるように感じます。社内でポッドキャストなどの施策を紹介すると反応はありますが、まだ社内にはピンときていない人もいたりします。そこはこれから広がっていくと思っています。SONのポッドキャストの中でも「関係する人の継続性」みたいな広がりはBAの中でですけど、起こっているかなって思います。
最近では、ピンバッジを製作して社内外に発信していこうという動きもあります。

SONのポッドキャスト施策、その狙いと目指す未来
ポッドキャストを聴いてどう感じましたか?
小山:やっぱり、音声メディア ✕ やまだひさしさんは強いなと感じました。話し方のテンポ、引き出し方、場の雰囲気のつくり方、どれもさすがという感じでした。内容を知っている自分でも、「こんな切り口で聞いてくるのか」と驚かされる場面も多くて、声だからこそ伝わる温度感がありましたね。
森住:そうそう。本当に完全に引きこまれたのは、宮本亜門以来かな(笑)。自分はSONに関わっていて情報もある程度知っているはずなのに、完全に引き込まれたというか。話し手の言葉に感情がこもっていて、知っている内容でも改めて感動するような、不思議な体験でした。
富本:やまだひさしさんの最初の「突然ですが〜」っていう出だしが、キャッチーでクセになる演出でしたよね。あのくだりが毎回繰り返されることで、“この番組だ”という安心感も生まれていて、非常にうまい構成だなと感じました。
谷口:私も普段ポッドキャストは聞きませんが、Spotifyで気軽にアクセスできたのがよかったです。エピソードの中には、私が現場で関わったプロジェクトの話もあり「そうそう、あの時のことだ!」と懐かしく思い出しながら聴いておりました。あと、2歳からでも参加できるなど意外と知らない情報もあって、リスナーとして純粋に楽しめました。
佐藤:やまだひさしさんが“リスナーの代表”としてわからない言葉をしっかり聞き返してくれるから、とても理解しやすかったです。専門用語や制度の話なども、噛み砕いて説明されていて、知識がない人でも入りやすい構成になっていると感じました。

ポッドキャストという施策の背景や目的について、どう捉えていますか?
森住:やっぱり第一の目的は「スペシャルオリンピックスって何?」という素朴な問いに答えることだと思います。世の中にはまだまだ知られていない中で、まずは知ってもらう。そのために声という手段を選んだのはとても理にかなっているなと。
谷口:その上で「Be with allⓇ」というスローガンをポッドキャストの中で何度も伝えていたのが印象的でした。これは“for”ではなく“with”であるという哲学で、言葉で聞くことでより深く伝わるものがあると感じました。ポッドキャスト中では、いろいろなゲストや関わった人たちと、そういった思いであったりとか、実際どういう取り組みだとかを会話の中から伝えているんだなと感じました。
小山:結構、ポッドキャストの中では、わりと踏み込んだ話題も多くて情報としても質が高い発言があったと思っています。オリンピック・パラリンピックとSOの違いや、なぜSONが「声」で発信しようとしているのかといった背景にも触れられていました。Be with allⓇの考え方や伝えたいメッセージだけでなく、だから私たちはこのように行動している、こういう思いでいるという部分も伝えたいという想いが、回を通して出演されたみなさんに共通しているなっていうのはすごく感じました。
佐藤:先ほどの話とも被るんですが、Webサイトを運用していく中でも担当者の方が、「活動をどんどん広めていきたいです」という想いをいつも伝えてくださるので、それが考え方の中心にあるんだろうなって私も感じています。
SNSでは自分から情報を探さない限りなかなか届きにくいけれど、ポッドキャストやラジオのように“流し聞き”できるものは、偶然の出会いが生まれることが多いと感じています。SONのような活動こそ、そういうメディアで広まる可能性は大いにあると感じました。
ポッドキャストを聴いて、印象に残った回やメッセージ
印象に残った回やメッセージがあれば教えてください。
谷口:私は、第3回にゲスト登場された平岡 拓晃(SON理事長)さんのエピソードが心に残っています。Be with allⓇのスローガンに込められた想いについて語っていた部分で、「挑戦には必ず多くの失敗が伴う。この失敗をネガティブに捉えるのではなく、失敗した人もいかに一緒にプラスに考え、その失敗を共有し支え合いながら、乗り越えていける社会を目指していく」というメッセージがすごく響きました。これはスポーツだけでなく、日常生活や社会活動すべてに通じる価値観だなと思いました。
森住:第5回のゲスト、小塚 崇彦(SONドリームサポーター)さんの花火と音楽を使った別のイベント「芸術花火」の企画の話が印象深いですね。イベントにアスリートたちを招待し観てもらうだけでなく、終了後には椅子の片付けなどのボランティア活動にも参加してもらったという話をされていて、「与えられる側」ではなく「与える側」としてアスリートが扱われていたことがとても印象的でした。また、アスリートが社会に対して関われる場所を小塚さんが提供し、相互に理解できる機会を創造したという話もすごく興味深かったし、まさに“Be with allⓇ”を体現していると感じました。
佐藤:私は、第6回のアスリートアンバサダーの方々(第4期の猪熊 祐希さん、稲山 芙雨珂さん、仲江 政志さん、伊藤 うららさん、三上 隼人さん)の声が直接聞けたのが嬉しかったです。顔と名前はWebサイトで見たことがあっても、声で語られる体験や気持ちはよりリアルで、「ああ、この人たちは楽しんでSONの活動に関わっているんだな」と感じられました。
小山:第7回のゲスト有森 裕子(SONユニファイドスポーツ®アンバサダー)さんの「Be with allであって、Be for allではない」「そもそも誰かのために何かするみたいな考え方じゃない」という言葉がとても印象に残っています。有森さんの言葉に力がこもっていて、メッセージが深く心に響きました。以前、有森さんが理事長時代にBAにお越しいただいた際にお会いした時の印象にも違わず、先日参加したスポンサー表彰のシンポジウムの際も「エンパワーっ!」とおっしゃっていて、そのパワーがひしひしと伝わってくる番組だったなと思いました。
あと、ポッドキャストの最後の方で「企業がスポーツを通してスポンサードする意味って何?」という話もあり、ナショナルスポンサーとしてBAがSONと関わっていることの意義や、スポーツが果たす役割について、あらためて考えるきっかけになりました。

SONやポッドキャスト等の取り組みについて今後の展望と期待
SONやポッドキャストに今後どのような展開を期待しますか?
佐藤:やまだひさしさんも番組内で何度か発言されていましたが、SONのラジオ放送が実現するといいなと思っています。SNSやWebでは、キーワードなど情報のかけらを知っている人には、関連情報が届きやすい仕組みになっています。例えば、検索のサジェストで、ひとつのキーワードに対して関連する情報を得られたり、検索ワードに関連した広告やニュースが届いたりと、関連情報は非常に手に入りやすいです。
逆に、全く何も知らない領域や、自分が調べようとしない領域に関した情報は届きにくいのですが、ラジオやCMのように流していたら聞こえてくるメディアなら、届けられる可能性があると考えます。アクションしなくても、受動的に情報が入ってくるような形も利用してSONの活動が多くの人に届いてほしいです。
森住:その先はもう組織とか関係なしに、Be with allⓇの考え方が、特別なものではなく“当たり前”になる社会になっていくといいなと思っています。ポッドキャストはそのためのひとつのきっかけになるし、私自身もその当たり前の社会をつくる流れの一部、目指す一員でありたいと思っています。
谷口:ボランティアや取材の際、SONのアスリートたちによるバスケの試合を観戦する機会がありました。知的障害のある人(アスリート)と知的障害のない人(パートナー)が混合チームで試合を行うのですが、アスリートとパートナーが同チームで共存して、フォローしあったり、一緒に盛り上がっているのを見て、これがSONが実現しようとしているBe with allⓇなのだなと、深く心に響いたことを思い出します。Be with allⓇの考え方が浸透した社会がもっと広がっていくように、ポッドキャストなどを通じて、SONの活動がさらに注目され、広く知られていくと嬉しいです。
また、森住さんがおっしゃっていた「目指す一員でありたい」という言葉は、すごく素敵な言葉だったので私もその一員になりたいなって思います。
小山:ポッドキャストで語られていたように、“インクルージョン”は理念じゃなくて実践だと思います。SONと関わる中でそれを日常的に感じているし、これからも自分たちがそれを発信していく側でいたいと改めて感じました。
第3回の平岡さんがお話しされているんですけど、先入観があるっていうのは現実問題として絶対にあると思います。でもよく考えると、知的障害っていうひとつのキャラクター、なにかに突出した個性であるという話だと思っています。先入観があるのは、過去の経緯であり歴史でもあるので変えられない部分もあると思います。ポッドキャストではそれを受け入れた上で、どういう方向に私たちが進んでいきたいか、どういう想いをもって取り組んでいるかという話を、やまだひさしさんが軽快に喋る音声コンテンツとして伝えています。
受け取る側のリスナーも構えることなく受け入れやすく、腑に落ちるというか納得した上で同じ方向を向いていけるコンテンツだと思うので、言葉の定義を知るだけでもいいのでまずは一回聴いてもらいたいですね。
運営するWebサイトでも、届けたいメッセージをきちんと表現できるコンテンツとして、私たちも協力し続けていきたいと思っています。

まとめ——「声」でつながる、新しいコミュニケーションのあり方
今回の座談会では、SONという組織の魅力から、BAとの関係性、そしてポッドキャストという新たな発信手法に至るまで、さまざまな視点から語り合いました。
SONのポッドキャストは、単に情報を届けるためのツールではなく、「声」というパーソナルな手段を通じて、人の想いや価値観をまっすぐに伝えるメディアとして、大きな可能性をもっています。
やまだひさしさんの軽妙かつ深い問いかけに導かれる形で、SONの取り組みや、関わる人たちの熱量がじわじわと伝わってくる、そんな“体験するコンテンツ”として、多くのリスナーの心を動かしています。
そして、BAとしても、こうした取り組みを通じて「コミュニケーションの本質」や「支援のあり方」をあらためて考える機会となりました。情報を「正確に届ける」だけでなく、「誰のもとに、どんなふうに届けるか」を設計していくこと。そこに、私たちの果たすべき役割があると感じています。
今回の“ポッドキャスト聴いてみた座談会シリーズ”では、第1回「SONの姿勢や考え方」、第2回「伝え方の選択肢」、第3回「アクセシビリティ」とそれぞれ異なるテーマで座談会を行っています。ぜひ他の回もご覧ください。
- “for”じゃなく“with”の世界へ——SONのポッドキャストで感じた社会のカタチ(第1回・本記事)
- 音声か?動画か?──ポッドキャストから考える“伝え方”の選択肢(第2回)
- みんなが使いやすいWebについて──SONの取り組みを通じて考えてみる(第3回)
ポッドキャスト、ぜひ聴いてみてください!
SONのポッドキャスト全8回は、Podcast、Amazon Music、Spotifyにて好評配信中です。
アスリート、スタッフ、ドリームサポーター、アスリートアンバサダーなどそれぞれの立場から語られるリアルな声に、きっと新たな発見があるはずです。
TOKYO FMにてラジオ番組『5分では伝えきれないスペシャルオリンピックスの世界』がスタート
2025年7月からTOKYO FMにてラジオ番組『5分では伝えきれないスペシャルオリンピックスの世界』がスタートしました!
パーソナリティは、SON広報プロジェクトアンバサダーである「やまだひさし」さん。
SOに関わる様々な方をゲストに迎え、SONの魅力をもっと身近に感じられるように、楽しさや現状、応援の方法まで多角的にお届けするトーク番組です。共生社会のヒントがここに。
TOKYO FM 『5分では伝えきれないスペシャルオリンピックスの世界』
月曜〜木曜 20:55~21:00 ※7月1日(火)スタート
放送概要、放送ラインナップ、視聴方法などの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。
今後も、SONとの連携を通じて、“つながりを生むコミュニケーション”を社会に広げていくことができればと考えています。