受験生や保護者、高校教員といった受験に関係する人向けに大学が公開するサイトが「入試情報サイト」です。入試情報サイトには、募集要項やオープンキャンパス、学生生活など、入学前後に関する情報がまとまっており、多くの場合、一般向けの大学公式サイトとは別に用意されています。
コロナ禍をきっかけにして、大学と受験生とのコミュニケーションの形は大きく変わりました。それに伴って、入試情報サイトで伝えるべき情報や伝え方をあらためて見直す必要があります。
ここでは入試情報サイトについて説明す�るとともに、これからの受験生とのコミュニケーションの在り方についても考察します。
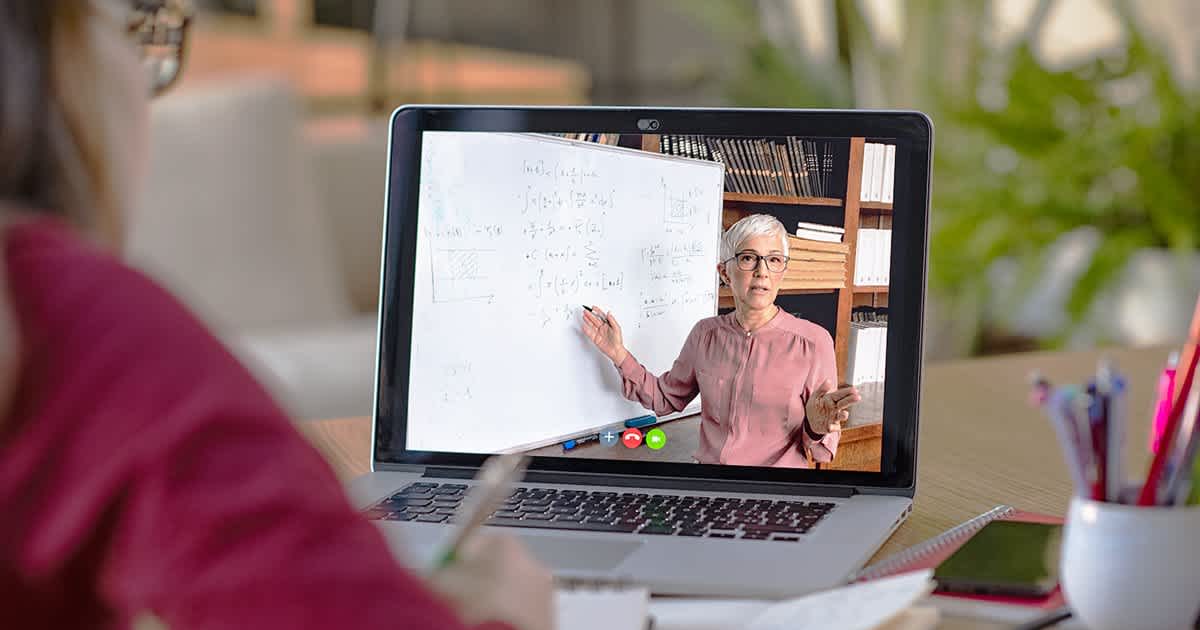
入試情報サイトの役割
入試情報サイトとは、主に大学入試に関する情報に特化したWebサイトのことです。もちろん、入試情報は大学の公式サイトにも載っています。しかし、公式サイトは、さまざまな人が見ることを想定して制作されているため、入試情報にだけ特化させるわけにはいきません。
そこで、受験生や保護者、高校教員といった受験に関わるステークホルダーを対象に、より入試や学生生活に特化した情報を発信するサイトが必要になるのです。
入試情報サイトの目的は、「大学の特徴や魅力をしっかりと伝えて志願者を増やす」ことです。そのために、一般的には次のようなコンテンツが必要となります。
入試情報
入試情報サイトには、入試の日程や試験会場、出願方法などに関する情報が必要です。大学入試は前期と後期に分かれることが多く、さらに大学入学共通テストの利用方式や推薦入試など、システムが複雑です。志願者にストレスをかけず、出願から入試へとスムーズに進んでもらえるよう、わかりやすく情報をまとめましょう。
オープンキャンパス情報
受験生に対して大学が施設を公開し、見学や説明会などを実施するイベントを「オープンキャンパス」といいます。受験生が学内の雰囲気を感じたり、施設を見て回ったりすることで、学生生活をよりリアルに体感でき、志望度が高まります。
オープンキャンパスでの体験が大学選びの決め手になる学生も多く、大学側も非常に力を入れるイベントのひとつです。オープンキャンパスの開催日程や会場などの情報は、入試情報サイトに必須の項目といえるでしょう。
入学後の勉強や進路・資格取得などの情報
入学後に大学でどのような勉強ができるのか、どのような資格取得が可能なのかといった、入学後に関する情報も入試情報サイトには必要です。
大学ごとに特色が出る部分なので、ほかの大学と最も差別化できるポイントでもあります。
学生生活(キャンパスライフ)情報
大学生活の醍醐味は、勉強だけではありません。サークル活動や学内外で開催されるさまざまなイベントといったキャンパスライフも学生生活の魅力です。
キャンパスライフは大学によって大きく異なるため、魅力的なイベントや充実したサークル活動があるのなら、しっかりアピールすることで、ほかの大学との差別化にもつながります。
先輩の声
実際に大学で学んでいる先輩の声も、用意しておきたいコンテンツです。受験生と近い視点を持った学生のリアルな声を伝えることで、「大学に入学したらどのような生活が待っているのか」を受験生にイメージしてもらうことができます。
高校教員向けのイベント情報
入試情報サイトを閲覧するのは、受験生だけではありません。進路指導を行っている高校教員も、入試情報サイトでさまざまな大学情報をチェックしています。
また、大学も高校教員を対象としたガイダンスや出張講義などのイベントを開催しています。進路指導に役立つ情報発信はもちろん、イベントの申し込みなどのタッチポイントを作っておくことが重要です。
就職情報
多くの大学生にとって、卒業前に待っている就職活動。企業とのつながりやOBとの関係を考えると、就職と大学には密接な関係があるといえます。そのため、多くの大学が就職実績を公開しています。
入試情報サイトにそうした情報を掲載しておくことで、就職実績を重視している受験生にアピールすることができるでしょう。
また、こうした重要なコンテンツの掲載を忘れないためにも、年間のスケジュールを予め立てておくことをお勧めします。
BAsixsでは、大学入試サイト担当者さまに向けた年間スケジュールのテンプレートをご用意しております。
大学入試担当者必見!年間スケジュールテンプレート(無料) | BAsixs(ベーシックス)
これからの大学が行うべきオンラインコミュニケーションとは?
コロナ禍をきっかけに、入試情報サイトの役割は大きく変わりました。説明会など、リアルでのコミュニケーションが難しくなり、大学は受験生とのコミュニケーションの多くを、オンラインに切り替える必要に迫られています。例えば、説明会やオープンキャンパスは現在、リアルではなかなか開催されず、代わりにオンライン会議ツールや動画配信などを通じて行われている場合もあります。
オンラインコミュニケーションは、コロナ禍でリアルコミュニケーションが難しくなった今だからこそ、入試情報サイトでカバーすべき大切な情報といえるでしょう。
オンライン化の傾向は、コロナ禍が収束した後も止まることはないと予想されます。というのも、オンラインコミュニケーションは決してリアルコミュニケーションの代替ではなく、リアルにはないメリットがあるからです。
遠方の受験生とも等しくコミュニケーションがとれる
オンラインコミュニケーションのメリットのひとつは、遠方の受験生ともコミュニケーションがとれることです。説明会やオープンキャンパスは、受験生に大学の魅力をアピールするための重要な施策ですが、実際のキャンパスで開催するとなると、遠方に住む受験生は、時間や金銭的コストで参加が難しい面がありました。
その点、オンラインであれば物理的な距離による差はありません。遠方の受験生も気軽に参加でき、大学にとってもより多くの志願者を獲得するチャンスが増すことになります。
少子化が進み、近隣地域だけでは志願者の獲得が難しくなった現在、遠方の受験生にアピールするためにも、オンラインコミュニケーションの充実は今後も必須となっていくでしょう。
問い合わせや出願を紙からオンラインに切り替えることでコスト削減につながる
受験生とのコミュニケーション以外でも、オンラインによる効率化を進めるメリットがあります。
例えば、問い合わせや出願など、紙や電話などアナログベースだった作業は、積極的にオンライン対応に切り替えていくべきでしょう。
チャットボットやFAQなどを設置することで、これまで必要だった作業が削減され、大学にとってもコスト削減につながります。
すべてをオンラインに置き換えられるわけではない
一方で、リアルコミュニケーションのすべてが、オンラインに置き換えられるものではありません。オープンキャンパスで大学を訪れて空気感や雰囲気を感じることや、研究室の設備を実際に見て確認することなど、すべてをオンラインで行うのは難しい面もあります。
オンラインコミュニケーションを充実させることで、反対にリアルでなければ難しいことも見えてくるはずです。どちらかだけに偏るのではなく、オンラインコミュニケーションとリアルコミュニケーション双方のメリットを取り入れることが肝要です。
オンラインコミュニケーション事例:東洋大学
前項で述べたような、オンラインコミュニケーションを実際に導入した入試情報サイトの事例をご紹介します。
東洋大学では、「志願者のニーズに合わせて入試情報を的確に表示する」というコンセプトで入試情報サイトをリニューアルしました。
志願者の情報収集のスタイルを考慮し、パソコンではなくモバイルファーストによるレスポンシブWebデザインを採用。サイトを訪問した志願者の行動を考慮して、ナビゲーションや検索機能を一から設計しました。
また、これまで紙で行っていた資料請求システムをデジタル化し、メールマガジン配信プラットフォームを構築するなど、受験生とのオンラインコミュニケーションの充実化を図っています。
入試情報サイトのデジタルシフトを進めた結果、少子化が進む中でも東洋大学は、2015年度から5年連続で志願者が増加しました。
大学入試担当者必見!年間スケジュールテンプレート(無料) | BAsixs(ベーシックス)
まとめ
入試情報サイトは、単に入試情報を掲載するためのサイトではなく、大学が望む人材に対してしっかりと情報を届けて、コミュニケーションを行うという役割を担っています。
オンラインコミュニケーションの重要性が増すこれからの時代においては、「とりあえずデジタル対応させる」のではなく、「大学としてこれからどうしていきたいのか、どのようなビジョンを描いているのか」をあらためて考えた上でデジタル化に取り組む必要があります。
BAsixsでは、豊富な実績にもとづき、大学入試サイトの構築・リニューアルをお手伝いすることが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

