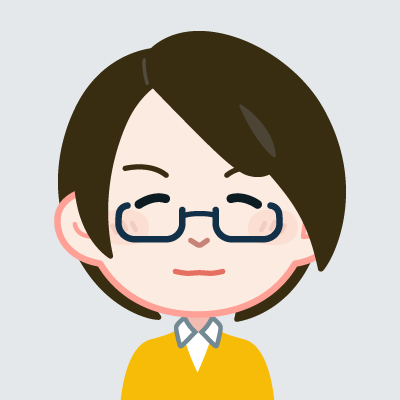経営課題の解決に向けた「上位戦略」を、現場で機能するWeb戦略や各部門の戦略へどう落とし込むのか。そんな悩みを抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。本記事は「戦略と実行」をテーマにした前後編の後編。
Business Architects(ビジネス・アーキテクツ、以下、BA)は、戦略設計に強みを持つ株式会社エクスペリエンスと統合し、戦略設計から実装・運用までを一気通貫で伴走できる体制を整えました。
後編では、統合によって拡張した支援領域を起点に、戦略と実行の融合を実現する新生BAの「共創のかたち」を解き明かします。
新生BAの“共創”のかたち
- 前編:「上位戦略」と「Web戦略」がつながるとき
- 後編:「なにをどう相談すればいいのか」から一緒に考える(本記事)

インタビューを受けた人
![プロフィールアイコン(イラスト):デザイン&コミュニケーションサービス事業部 事業部長 小山]()
- 小山デザイン&コミュニケーションサービス事業部/事業部長(ビジネス・アーキテク��ツ)
toCサービス、toBサービス拠点マネジメントを通してサービスの複数拠点の運営管理を担当。またtoBサービスの企画立案などで企業向けサービスの企画・開発を行う。Business Architectsには2019年にジョイン。大規模サイトのアカウントマネジメントや金融系サイトのプロジェクトマネジメントなど多くのプロジェクトを手掛ける。
![プロフィールアイコン(写真):エクスペリエンス事業部/事業部長(ビジネス・アーキテクツ) 新山 佳世子]()
- 新山 佳世子エクスペリエンス事業部/事業部長(ビジネス・アーキテクツ)
事業会社にてWeb部門立ち上げ、Webサイト制作会社にてインフォメーションアーキテクトを経験。国内大企業、グローバル企業の大規模プロジェクトを手がけた後、エクスペリエンスへ入社。チーフコンサルタント、プロジェクトマネージャーとして、プロジェクト全体を牽引。2020年、マネージャーを経て取締役就任。2025年ビジネス・アーキテクツへジョイン。
「戦略」と「実行」の融合で拡張した支援領域
戦略設計に強みをもつエクスペリエンスとの統合によって、BAが提供できる価値はどのように広がったのでしょうか?
小山:やはり、提案できる領域が拡がりましたね。今まで「RFP(提案依頼書)を受けてからがスタート」だったプロジェクトが、「お客さまの戦略がまだ曖昧な段階」から始められるようになりました。
しかも、そこから戦略設計〜実装〜運用までを一気通貫で支援できる。提案の段階で、戦略側と制作側の人間が揃っていて、それぞれの目線から問いを投げられる。これが、プロジェクトの解像度を一気に上げるのではないかと考えています。
新山:既存のお客さまからもポジティブな反応がありました。具体的には、「実際の制作についてもお願いできるんですね!」「前段の意図や思いを踏まえて制作できそうで安心感がありますね」などの声をいただきました。
また、BAはこれまで大型プロジェクトを得意としていたこともあり、大規模なCMSでの構築やAEM(Adobe Experience Manager)の導入を相談できることなど、さらにお客さまに安心いただける環境になったと感じています。

まだ統合して間もない時期(2025年8月取材)ではありますが、新たに挑戦していきたい領域はどこでしょうか?
新山:今後ますます、戦略設計の領域でも「生成AI」や「AIエージェント」、「RAG(検索拡張生成)」の活用が進んでいくはずです。コンテンツ制作やデータ分析業務、施策のプランニングなど、その範囲は多岐に渡ります。
そのうえで、お客さまの状況や目指す姿を理解している私たちだからこそ、「どうお客さまの事業に落とし込むのか」を模索していけるのではないかと考えています。
小山:そうですね。企業規模が大きくなれば、AIなどのツールやシステムを簡単に導入するわけにもいかず、信頼性や安全性の担保は不可欠です。
だからこそ、導入に際してのボトルネックの解消や導入後の効果検証といった部分をしっかりと把握し、伴走するパートナーが必要だと考えています。
あくまでAIは「意思決定のサポートツール」です。これからは、AIが考えたものに対して、どういう基準で意思決定するのかという部分が重要だと感じます。その大きな選択を一緒に考えていける存在でありたいですね。
新山:ほかにも、「ソフトスキル」をどう向上させるのかという部分にも挑戦していきたいですね。具体的には、コミュニケーション能力やリーダーシップ、問題解決能力など、「専門知識や技術以外の能力」のことです。
AI活用や自動化が進む中では、企業内部のコミュニケーションや個人の適性・マインドセットなどの「定性的」な部分がさらに重要になってくるはずです。そのため、今後は「組織作り」に特化したサービスが求められるのではないかと感じています。

お客さまと“共に設計する”
お客さまと戦略設計をしていくうえで、大事にしていることは何ですか?
新山:前編でお話しした「視座・視野・視点」を合わせるというのはもちろんですが、やりとりしている担当者の「機微」も意識しています。私たちが提案したことに対しての反応や興味の有無など、担当者が納得して進められるかというのも重要だと考えています。
また、言葉の定義も大事にしています。たとえば「デザイン」という言葉1つとっても、ビジュアルや見た目としての「デザイン」で使う人もいれば、体験やサービス設計全体やそのプロセスとしての「デザイン」を使う方もいる。
そういった、個人の立場で意味が変わりそうな言葉については、認識のズレを防ぐためにも慎重にすり合わせするようにしています。
なかには、「自分たちにどんな課題があるかも分からない」というお客さまもいるかと思います。そういった、かなり前段の情報から与件整理をする際に意識しているポイントがあればお聞かせください。
小山:先ほどの新山さんの「言葉の定義」の話にもつながりますが、難しい言葉や曖昧な言葉を外すと、課題が見えやすくなることは多いです。
たとえば、「UI/UXがよくない」と言われた場合、その本質を紐解いていきます。紐解いていくと、ユーザー体験ではなく単なるビジュアル的なデザインに納得されていないという場合も多いんです。
一方で、紐解いた結果「導線が分かりにくい」という指摘であれば、データを分析し「問い合わせフォームで90%が離脱している」というように課題を具体化していく。課題の解像度を高めていくことで、現場で機能する言葉に落とし込むのが大切だと思います。
新山:基本的にどんなお客さまでも、「現状把握」から入ることが多いです。というのも、「本当にそれが課題なのか」「そもそも同じ目線じゃないんじゃないか」を確認する必要があるからです。
その際、担当者だけでなく、ステークホルダー全体へのヒアリングやインタビューを行います。時にはエンドユーザーへのヒアリングやユーザーテストをすることもありますね。
与件段階でいただいたものが課題であればもちろんそこに向けて動けますが、最初の段階では「課題自体が共通認識になっていない」というケースも多いんです。そこを丁寧に言語化していくのが、最初のステップですね。

「未来の意思決定」をサポートする
AIなどのテクノロジー活用が加速していく中で、どんな「設計力」が重要になると思いますか?
小山:「デジタルを超えた設計力」は必要になると思いますね。WebサイトもAIも、結局はデジタルの話です。でも、ユーザー体験はリアルな世界でも行われていて、そこを見据えた設計は必ず必要になります。
たとえば、「このコンテンツをうまく伝えるためには、紙の方がよいんじゃないか?」といった、デジタルに閉じない視点の設計力は重要になると感じます。
新山:私は「組織やプロジェクトの設計力」が重要になると考えています。
大きな企業だと、「昔は広報部署だったけど今はWebの部署になった」「所属部署の名前が変わったけど内容は変わっていない」ということが往々にしてあるはずです。企業として成し遂げたい目的に沿った組織をどう設計するのか、は大切になると感じています。
知識やリテラシーももちろんですが、そのプロジェクトをドライブするためには「どんなリーダーシップが必要なのか」「どんなマインドを持った人が適性なのか」を踏まえて、組織を設計することが求められるのではないでしょうか。
あらためて、これからお客さまにどのような価値を提供していきたいですか?
新山:お客さまを取り巻く環境は日々変化しています。テクノロジーの話ももちろんですが、業界における人材不足やグローバルへの対応など、考えなくてはならないことも増えています。
そんな状況で、デジタル領域がどうビジネスに貢献できるのかを考える。お客さまの事業をより成長させるために、デジタルという「武器」の使い方を安心して聞ける存在でありたいと思っています。
小山:私たちはお客さま以上にお客さまのプロフェッショナルにはなれません。もちろん、そうありたいとは思いますが、やはりお客さまのことはお客さま自身が一番把握されているはずです。
だからこそ、現場でプロジェクトを動かすプロフェッショナルとして、第三者だから気づくことがある。
今回の統合で、戦略の初期段階から伴走し、実際の制作まで一貫してできるようになりました。これによって、お客さまの「未来の意思決定」をより高い精度でサポートできると考えていますので引き続きよろしくお願いします。

編集後記
「まず何を相談すればいいか分からない」。企業担当者の中には、そのような悩みを抱えている人もいるかもしれない。今回の後編で印象的だったのは、小山さんと新山さんがたびたび口にした「言葉の定義を揃える」ということ。
UI/UX、デザインやAI活用など、同じ単語でも立場によって解釈は異なります。だからこそ、課題を具体化しながら目線を合わせ、戦略と制作を一気通貫で設計していく。統合後のBAはより一層、お客さまの意思決定をサポートできるようになります。
前編( 「上位戦略」と「Web戦略」がつながるとき──新生BAの“共創”のかたち)では、「上位戦略とWeb戦略の分断」にまつわるよくある課題やその背景を紐解きながら、プロジェクトをドライブさせるための考え方や進め方を語っています。ぜひご一読ください。