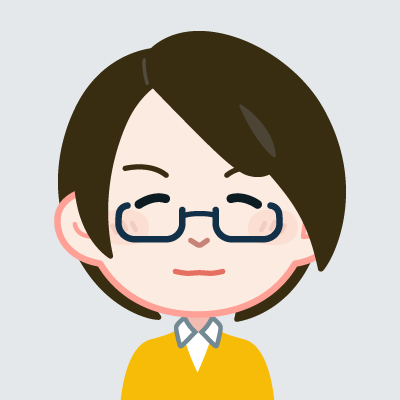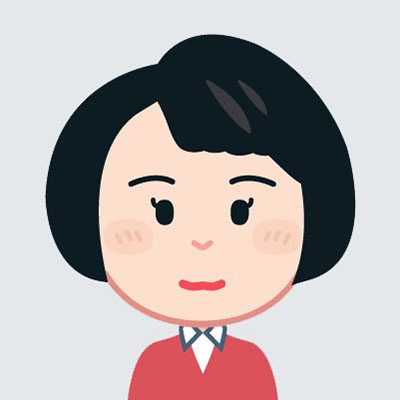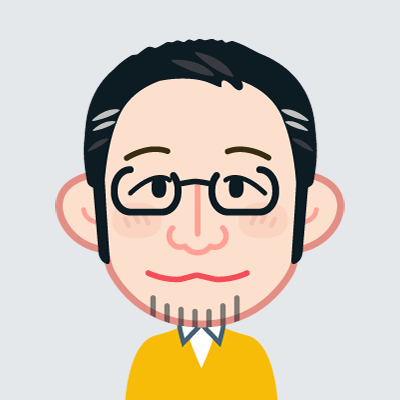Webサイトの制作や運用におけるアクセシビリティの取り組みは、チェックリストを満たすだけでは不十分です。大切なのは、「なぜ必要なのか」をチーム全体で共有し、要件定義から運用に至るまでプロジェクトにどう組み込むかという視点です。
さらに、お客さまに伝えながら、日々の更新や運用の中でも意識を継続させ、組織として自然に定着させていく工夫も欠かせません。そうした積み重ねこそが、アクセシビリティを“あたりまえの品質”にしていく第一歩です。
後編でも、Webサイト制作の現場で活躍するBusiness Architects(ビジネス・アーキテクツ、以下BA)のデザイナー・エンジニア・ディレクターの4名が登場。現場での工夫やチーム連携、社内啓蒙の実例を語りながら、アクセシビリティを組織に根づかせるヒントを探ります。
使いやすいって、誰にとって?
- 【前編】Webサイトのアクセシビリティを考える
- 【後編】アクセシビリティ対応をサイト制作の“あたりまえ”に(本記事)

インタビューを受けた人
![プロフィールアイコン(写真):デザイナー 水戸]()
- 水戸クリエイティブグループ/リーダー/デザイナー(ビジネス・アーキテクツ)
Web制作会社数社でのデザイン経験を経て2017年にBA入社。入社後はLP〜大規模な案件まで複数案件の情報設計・デザインに携わり、現在はこれまでの経験を活かして客先常駐中。2020年 UD検定初級、2023年 人間中心設計スペシャリストの資格取得。 人に恵まれていることに感謝しつつ、毎日やりがいと面白さを感じながら課題解決のために日々奮闘しています。
![プロフィールアイコン(イラスト):シニアディレクター、Web解析士 齊藤]()
- 齊藤アカウント&ディレクショングループ/リーダー/シニアディレクター、Web解析士(ビジネス・アーキテクツ)
Web業界20年。デザイン、コーディング等を経験し、現在は金融系のUI/UX開発のディレクターを担当。NISAやiDeCoの利用で初めて投資をおこなうエンドユーザーにもわかりやすく目的の行動がどれる�ような情報設計をめざして日々取り組んでおります。
![プロフィールアイコン(イラスト):ディレクター、WEB解析士 滝沢]()
- 滝沢アカウント&ディレクショングループ/ディレクター、WEB解析士(ビジネス・アーキテクツ)
IT系企業にてwebデザイン・コーディング・ディレクション・デジタルマーケティングなど幅広く経験した後、2020年BAに入社。webディレクターとしてサイトの制作・運用の他、サイト改善にも携わっている。
![プロフィールアイコン(イラスト):フロントエンドエンジニア 小宮山]()
- 小宮山Webエンジニアリンググループ/テックリード/フロントエンドエンジニア(ビジネス・アーキテクツ)
およそ20年フロントエンド実装を専門に活動。一部上場企業のグローバルウェブガバナンス基盤整備を主に手がける。プロジェクトにおいてはテンプレートやコンポーネント開発を中心に担当。ユーザビリティやアクセシビリティ、SEOといったフロントエンド周辺技術に関する造詣も深い。
「アクセシビリティへの取り組み」が企業にもたらす価値とは?
前編では、「BAのアクセシビリティへの向き合い方」を伺いました。後編では、実際のプロジェクトの進め方についてお聞きしていきたいと思います。まず、アクセシビリティ対応における一番のポイントはどこになるのでしょうか。
滝沢:まず要件定義の段階で、アクセシビリティ方針を決定することが大事です。適合レベルは「AA」なのか、それとも「A」で充分なのか。目指す基準も「準拠」なのか「一部準拠」なのか。目標到達地点を明確にすることで、作業効率やアクセシビリティチェックの精度が上がります。
また、アクセシビリティ方針をWebサイトに掲載する場合は、社内のアクセシビリティスペシャリストや外部の専門業者に「Web Content Accessibility Guidelines(WCAG)」のチェック項目をクリアしているか精査してもらうのですが、大半の場合は、なんらかのフィードバックが戻ってきます。
そのフィードバックのレベルに応じて、どこまでをスコープ内とするのか、事前にお客さまと意識を合わせておくことが重要です。
小宮山:たしかに要件定義ではっきり決まっていると、エンジニアとしても助かりますね。たとえば、「AA 準拠」といわれたら確認事項が明確になって、仕事の進め方が全然変わってきます。
齊藤:アクセシビリティ対応が要件として決まったら、ディレクターはもちろん、デザイナーやエンジニアもある程度の知見やスキルを持って取り組むことが求められます。
私が携わっている大手証券会社のWebサイトでは、「AA 準拠」を目指しました。その際には、外部の専門業者からPDFで数十ページにもおよぶフィードバックが戻ってくるので、それを見越してスケジュールと体制を組む必要がありました。

お客さまに「アクセシビリティへの取り組み」の必要性を理解してもらうために、何か工夫していることはありますか?
滝沢:Webサイトの構築はBAが担当し、その後の運用はお客さま側で行っていただくという案件も珍しくありません。
そういった場合、何もルール化されていないと、運用していくにつれてアクセシビリティ対応のできていないページを制作してしまう可能性があります。
そのため、画像作成をする際の注意点やALT(代替テキスト)の設定方法など、Webサイト更新のためのマニュアルと合わせて、アクセシビリティ面の注意をお伝えするようにしています。
水戸:私の場合、もともとアクセシビリティへの取り組みに前向きなお客さまとお仕事することが多いため、特別な工夫をしているわけではありません。
ただ、私自身はアクセシビリティ対応を「誰もが安心して使えるサービスを実現するための基本的な視点」として常に意識しています。
必要性をお伝えする際には、「法的に必要だから」「義務だから」というよりも、「この文字色と背景色の組み合わせだと、視力が弱い方には読みづらいかもしれません」といったように、具体的なユーザー体験に置き換えて伝えるようにしています。
ユーザー体験に置き換えてお伝えすることで、お客さまにも共感していただきやすくなると感じています。
齊藤:アクセシビリティへの取り組みは、Webサイトの担当者だけが取り組むものではなく、「誰もが使えるサービスを提供するためのチーム全体の共通認識」と捉えてもらうことが重要だと思っています。
そのため、具体的なユーザー像やよくある困りごとなどを例に挙げて共有すると、「うちのWebサイトの利用者にもいるかもしれない」とお客さまも想像しやすくなるかもしれません。
お客さまのビジネスの延長線上にあるものとして、「アクセシビリティへの取り組み」のメリットや効果を説明すると納得感も変わってきそうですね。
齊藤:そうです。アクセシビリティへの取り組みを「義務」と考えているお客さまも少なくありませんが、対応によってUXが向上すればユーザーが幸せになれるだけでなく、業務効率やお問い合わせの削減、CVR(コンバージョン率)の改善も期待できます。
さらに、「すべてのユーザーに公平な機会を提供する」という企業姿勢を示すことは、ブランド価値や社会的信用を高め、エンゲージメントの向上にもつながります。
アクセシビリティへの取り組みは、「コスト」ではなく「投資」として捉え、その視点でお客さまに伝えていくことが重要だと感じています。
アクセシビリティへの取り組みをチームや組織のあたりまえに
ここまでお話を伺って、皆さんのアクセシビリティへの意識がとても高いと感じました。全社的にそうなのでしょうか?
水戸:基本的にメンバーのほとんどがアクセシビリティに対して高い意識を持っていると思います。
また、日々のコミュニケーションのなかでも「この配色、コントラスト比は問題ない?」など、ちょっとした確認や気づきが自然とやりとりされる環境なので、アクセシビリティが特別な対応ではなく、日常的な設計判断の一部として定着していると感じています。
齊藤:とはいえ、BAメンバー間でも個人差はあります。だからこそ、知見のあるメンバーが積極的に意義を伝え、全体に広げていくことが大切だと思っています。
たとえば、以前、若年層向けのWebサイトを構築する案件で、デザイナーから薄いグレー文字を用いたデザイン案が出たことがありました。ビジュアル的な洗練を優先したものでしたが、私は「一部のユーザーには可読性が低いのでは」と感じました。
単に「高齢者には読みにくい」と伝えると「若年層向けだから問題ない」と折り合いがつかない可能性もあります。
そこで、「通勤中の若者でも、日差しや逆光でスマホ画面が見づらくなることがある」と例を出したところ、「たしかに、そうだね」と納得してもらえました。

まさに「誰にとっても使いやすい」という視点でのフィードバックですね。
小宮山:今の齊藤さんの話が象徴的だと思いますが、「WCAGに準拠して」などというと、「アクセシビリティは特別な対応」という感じで構えてしまいます。
「誰にとってもフラットで安心できる設計」と捉えてもらう。そのためには、社内で啓蒙し続けるというのは重要だと感じます。
BAは中途入社のメンバーも多いですし、時代によって法令やガイドラインが変わり続けていくなかで、最新情報を社内周知して共有していく。実際にBAでは「分科会」と称して、各領域で専門的な知識を学べるグループワークを開催しており、アクセシビリティ分科会もその一つです。アクセシビリティに対する意識が高いメンバーが多いのは、こうした活動を継続していることも大きな要因です。
「使いやすさ」を問い続ける
今回、さまざまな職種の方と「アクセシビリティの取り組みや実践」をテーマに話していただきました。感想や印象的だったことをお聞かせください。
齊藤:企画立案の段階で「使いやすさ」への意識がやや薄れかけていた部分がありましたが、滝沢さんの「要件定義でしっかり到達点を決め、メンバー全員で共有することが大切」というお話を伺い、改めて意識を高めるきっかけになりました。
滝沢:アクセシビリティへの取り組みや対応内容に対するリテラシーがそれほど高くないお客さまもいらっしゃいます。そうした方々に寄り添って、アクセシビリティの重要性や価値を発信していくことにも積極的に取り組んでいきたいと思いました。もちろん、社内での知見やスキルの共有、深化も加速させていきます。
水戸:BAのメンバーは最低限のアクセシビリティの知識は持っていると思うのですが、実際の現場では個々人の理解度や捉え方にまだ差があると感じています。
アクセシビリティは特別な専門分野というより、日々の設計や確認作業のなかに自然と組み込まれるべき考え方です。その感覚をチーム全体で共有できれば、より一貫性のあるアウトプットにつながるはずです。
そのために、BA全体で意識を底上げするような啓蒙活動に取り組み、自分自身がこれまで経験してきた「なぜ配色や文言ひとつがユーザー体験を左右するのか」といった具体的な事例を積極的に伝えていきたいと思いました。
小宮山:私は、そもそも「アクセシビリティ」というテーマで話し合えたことが良かったですね。こういった議論を社内はもちろん、社外の方とも活発にしていきたいですね。
また、エンジニアの立場からも、アクセシビリティについてお客さまに説明する機会を増やせるのではないかと感じました。ディレクターやデザイナーとはまた違った視点で、その必要性や価値を伝えられるはずです。
では最後に、BAの進めるアクセシビリティへの取り組みが、最終的にプロジェクトやお客さま、その先のユーザーにもたらす価値は何だと思いますか?
齊藤:まず、アクセシビリティへの取り組みがプロジェクトにもたらす大きな価値は、設計の根拠が明確になり、チーム内の意思統一が図れることです。「なんとなく使いやすそう」ではなく、「誰にとってどう役立つか?」を言語化できるため、判断軸が揃います。
お客さまへの提供価値は、機会損失を未然に防げる可能性が高くなることです。アクセシビリティが配慮されていないと、多くの潜在ユーザーを無意識に取りこぼしてしまう恐れがあります。それは、サービスの利用率や顧客満足度に直結し、最終的には収益性にも大きく関わってくる問題です。
そして最後にユーザーにもたらす価値については、やはり「使いやすさ」です。それは、年齢や障がいの有無を問いません。たとえば、片手がふさがっている、通信環境が悪いといった一時的に困った状況でも、「ちゃんと伝わる」「ちゃんと操作できる」という体験をユーザーに提供できます。
アクセシビリティへの取り組みは、特定の人のための、特別な対応ではないと思います。「誰のために、なぜこの設計にしたのか?」という問いを常に持ち続けること。その姿勢で、BAは今後もノウハウと知見を蓄積しながら、Webの体験をアップデートしていきます。

「特別な対応」から「あたりまえの品質」へ
後編での気づきは、アクセシビリティを「一度きりのチェック」や「特別な対応」として消費するのではなく、プロジェクトや組織に根づかせていく視点の大切さです。
要件定義の段階で目標を明確にすること。お客さまに具体的な利用シーンを伝えること。そして日々のコミュニケーションのなかで自然に意識を共有していくこと。そうした積み重ねが、アクセシビリティを“あたりまえの品質”として育てていきます。
アクセシビリティは「コスト」ではなく「投資」です。ユーザーに安心できる体験を届けることは、ブランド価値の向上やビジネス成果に直結します。特別な配慮ではなく、「誰のために、なぜこの設計にしたのか?」という問いを持ち続ける姿勢こそが品質を支え、結果としてユーザー体験の向上や機会損失の防止につながるのです。